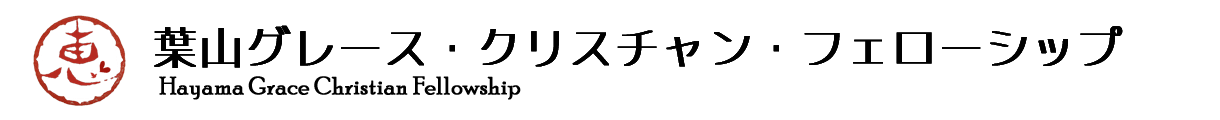髙橋保行著「ギリシャ正教」(講談社学術文庫 講談社 1980年)の中に、次のように書かれているのを読みました。
神の力と働きに人があずかり、神と交わりを持つとき、はじめて人間とよばれうるものとなるというギリシャ正教の人間観は、ただたんに創られたまま、あるがままの形で存続するだけでは人間とは考えないことを意味する。これは、すでにみたように、人間の生死の問題を、肉体や霊魂の生死という現象面からでなく、人間と神の関係から解こうとするからである。ギリシャ正教の世界で、人の生死の判断を究極的な意味においてくだすときには、過去においても、現実においても、人が神の力と働きにあずかっているかいないかが基準とされるのである。
髙橋保行著「ギリシャ正教」(講談社学術文庫 講談社 1980年 p.258)
ここで問題となる人間の創られたままの形と、人間が神との交わりの中に生きつつあるものとなるという過程の関係を、表信者聖マキシマスは、創世記の中の像と肖という言葉にみいだしている。われわれの像と肖に似せて人を創ろうという神の言葉から、聖マキシマスは、人間の創られたままの形を像、創られた人間が神の力と働きにあずかり、神との交わりの中に生きる過程を肖と解釈するのである。この解釈は、人が人とよばれるには、神の力と働きの中に生きつつあるというプロセスをもっていなければならないことを意味する。霊と体が存続するだけではなく、神に向かって生きつづけるという上昇のムーヴメントがなければ人間とはよばれないのである。
この世に生まれてくる者はすべて神の像をもっているが、肖はこの世に生きるときに、人が神との交わりにより、自分の意志と力で自分の中に築きあげてゆくものである。生まれながらに与えられている像と肖のうち、像は人間がどんな人生を送ろうが消えないが、肖は人が意志と力により自分の中にとりいれなければならない。像と肖は、共に神の恩恵により与えられるが、肖のほうは人生の途上で、人がみずからの中に神との交わりにより形成するものである。
人が自分の意志と力で神の肖をとりつつ生きるとき、はじめて神の像と肖をもつ総合的な人間が生まれる。
先の投稿との関連ですが….生まれながらに「アブラハムの子孫」という意識だけでなく、アブラハムの祝福を継承するものとして生きる、「神との生きた関連性」がなければ、確かにアブラハムの子孫である事実は事実だけれども、その実が残らないのだろうと思います。
何を見ているのか、何を感じているのか、何を伝えたいと思っているのか….
心に思い浮かぶ思いを全て書き記すことも、表現することも出来ないように思いますが、それでも分かち合うために書き残す努力を忘れないでいたいと願っています。