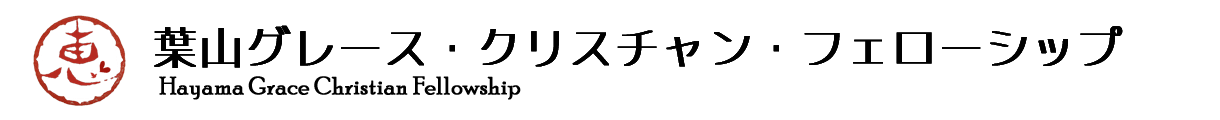1913年3月29日の「女子英学塾」での卒業式の式辞の一部を耳にしました。
One great beacon light is Truth. It will shine in every one of our souls, if only we do not refuse to see. It points out to us our own shallow attainments, our petty meannesses, our selfishness, vanity or jealousy; and reveals to us the good in others. Thus we may escape the rocks of pride and self-love.
Follow also the guiding lights of Love and Devotion. In women, these are called instincts, but yet how narrow often is our love, how fickle and shallow, our devotion. Learn to love broadly, deeply and devotedly, and your lives can not fail. With nobler desires, greater earnestness and wider sympathy not limited to just a few, but taking in the many even beyond the home, the weakest of us may attain success.
一つの大きな道標となる光が「真理」です。私たちが見ることを拒みさえしなければ、それは私たちの魂の中で輝いています。この光は、私たちの浅はかな達成感、些細な卑しさ、利己主義、虚栄心、嫉妬などを指摘し、他人の良いところを明らかにしてくれます。このようにして、私たちはプライドと自己愛の岩から逃れることができるのです。
また、「愛」と「献身」という導きの光にも従ってください。女性の場合、これらは本能と呼ばれますが、私たちの愛はどれほど狭く、献身はどれほど気まぐれで浅いものでしょうか。広く、深く、献身的に愛することを学べば、人生に失敗はないのです。より崇高な願望と、より大きな熱意と、より広い共感をもって、一部の人だけでなく、家庭を超えた多くの人を巻き込むことで、最も弱い人間でも成功を収めることができるのです。
“beacon”をここでは「道標」(みちしるべ)と訳してみましたが、「灯台」と訳されるべきなのかもしれません。私たちの人生の中で闇を照らす光としての役割を果たしてくれる『真理』。